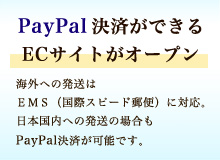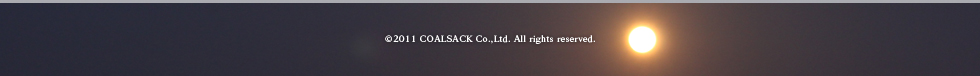<経歴>
1934年 札幌生まれ、札幌在住。
詩集『夜間飛行』『ハーレム・ノクターン』「秋の韓国で』『樹木』『人生の或る局面』『雪の聖母園』『異変』『喪失』『リラの花咲く樹の下で』『移動と配置』『斧を投げ出したラスコーリニコフ』『カナリアは何処か』。
詩と思想新人賞、北海道詩人協会賞、更科源蔵文学賞、などを受賞。
2010年 コールサック詩文庫『谷崎眞澄詩選集一五〇篇』。
日本現代詩人会、パンと薔薇、小樽詩話会、極光、各会員。
<詩作品>
夜間飛行
これは三人の男の概要だ
一九一四年九月二十二日
アラン・フルニエは
ベルダンの近くの森林にいた
彼は負傷してドイツ軍に運び去られた
一九四四年七月三十一日
サン・テグジュぺリはライトニングで
地中海上空にいた
彼は偵察任務についていた
一九四四年十二月二十五日
グレン・ミラーは
イギリスの或る飛行場から
旅客機でパリに向かっていた
旅客機は霧のドーバー海峡に消えた
これは三人の男の概要だ
これはだが三人の男の概要ではない
調べなくとも限りなく男の物語がある
まだ戻ってこない多くの男たちがいる
必ず帰ってくると待っていた男たちの母親は
ほとんど死んだが……。
雪の記憶
道は何処までも続き
その涯に いまは亡き祖父の入植地がある
暗い雑木林 軽便鉄道 水銀鉱山
それらが 私の幼い記憶の襞に
きれぎれに残っている
夜はランプだけが頼りであった
時折 祖父の家に集まる
一族の指という指は
すべて節くれだっていた
海を渡ってきた一族は
ふさわしい場所に入植したか
それは私の一族だけでなく
多くの入植者たちに言えることであった
何処に入植しても苦労は同じであった
開拓の夢は苛酷であり 私の一族も例外でなく
新天地を求めて 彷徨い続けた
楽しみは何ひとつとしてなく
位牌を取り出しては ぼやけた戒名を覗きこみ
幼くして死んだ者が多いのに
驚きあった
辿り着いた入植地は山峡の傾斜地であった
すべて鬱蒼とした森林
斧と鋸しかなかった
焼き畑の切り株と切り株の間に
ビートとハッカを植えた
冬は森林労働 それしかなかった
単調な生活の繰り返しから得たものは
都会への脱出であり
それを避けることは
一族の滅亡を意味した
きさらぎも末のある夜
私は祖父の入植地の傍を車で通った
祖父の家は見る影もなく崩れ落ち
雪明かりの雑木林のなかで私の血縁たちが
黙って酒盛りをしているのが
ちらっと見えた
近くに石北峠がある
ほどよい距離
夏の海辺の夕闇のなかに浮かぶ二人の影。
身じろぎもせずに夕日を凝視している。真っ赤に燃える球形の神秘を。
少年時代に自由に学ぶことが出来なかった父親。とてつもなく、暗い時代を過ごした男には、太陽も星も考えたことはなかった。それは、ほとんどの男と女に言えたことだ。生き残ったのは、偶然であった。
「太陽までの距離は一億五千万㎞、太陽に比べると、地球は、まるで〝けし粒〟みたいだ。ところが、太陽と地球は、ほどよい距離にあるんだ」
少年は、暗い時代をくぐり抜けてきた父親に話しかける。
―ほどよい距離か―
夜の星座を楽しむことの出来なかった父親は、ほどよい距離という言葉に、にっこりとした。
少年の頃、図書室にある理科の本は、限られていたし、家には、ぼろぼろの蟹工船しかなかった。
少年は、父親に星座について語った。星座について何ひとつ知らない父親は、黙って耳を傾けた。
夕日が、すっかり波の彼方に沈むと二人は岸辺を歩いた。
父親は、幼い頃の経験と記憶を語って聞かせた。
その夜、父親は、天体望遠鏡を買う約束をした。
少年は、そのうちに眠りに落ちた。
お互いに、ほどよい距離であった。
夏の夜の星座をテントの隙間から眺めたあと、父親は、我が子の寝顔を星明りのなかに見つめた。
異 変
異変は想像力で追いきれないことがある
冬の長野の空に
空の青 地の麦をシンボライズした国旗が
あざやかにひるがえった
ウクライナ
ウクライナのこどもたちの首に手術痕は
ふえているのではないか
みどりの森のサナトリウムの
無垢のひとみには
あの日の記憶はない?
イワンよ
ナタリアよ
多すぎて抱きかかえられない死よ
一九八六年四月二十六日 午前一時二十三分
チェルノブイリ第四号原子炉爆発
異変は地鳴りをあげて噴きあがり
垂直の火柱は黒煙となり
空を焦がし原子炉は燃えるにまかせ
噴きあがった死の灰は
チェルノブイリから世界じゅうにひろがっていった
ミルクと肉が
野菜と果物が
大地と地下水が
汚染するにまかせた
ひとびとは森の樹が真っ赤になり
魚が白銀のように光るのに驚いた
チェルノブイリ原発から三・五キロ離れたプリピアチ市 の
住民はだれもいなくなり
病院という病院が
重い症状のひとであふれた
ひとの身体はやわらかく傷つきやすい
身体は死の灰を吸う管となり
白血球も血球も壊れ
高熱で呻き 震えが襲い
血を吐き ついに遺体になるしかなかった
遺体は何処かへ消え
運んだ者も消え
彼らがどこでどうなったか
誰も知らない
そうして
放射能まみれの製品が
キャッチ・ボールのように動き
ひとびとはそれを知らずに買い
明るい電灯の下で冒された
いま原発三十キロ圏内にひと影がうろつく
死んだ森 死んだ川 死んだ畑
汚染のひどいところでも
ものを食べて生きていることに変わりはない
汚染された畑を耕して
トウモロコシやジャガイモ
林檎やイチゴなどの果物を植えて
視力を失いながら ひっそりと―
大地は荒野となってひろがり
夕日にちからはないが
春には太陽が輝き木の芽が吹く
夏にはドニエプル河のほとりでのピクニック
そのような光景と生活があるのだろう
いつのまにかわたしたちの住んでいる島は
原子炉で埋まっている
島は いつも船のように揺れることがある
そして 核燃料は見えない
匂いもない味もない
いつの日にか原子炉は ひびわれた石棺になる
わたしたちの時代の明確な歴史は
黒い雨のなかにあり
そのなかに
首をとおしているのを知らない
原子炉も核爆弾もそう変わらない
放射性廃棄物も
わたしたちは
ふかくふかく切れ込んだ活断層のうえに
すべりおちて行く
すべての消息は不明である
*参考文献・広瀬 隆 『危険な話』『チェルノブイリの少 年たち』ドキュメント・ノベル 新潮社
*十二年間のチェルノブイリの事故処理関係者三十五万人 死亡者一二、五一九人 一九九七年の死亡者二、一九七人
(道新1998.4.24朝刊)
冬の夜明け
寒さが厳しくなると
きまって納豆を売る少年の声が
聞こえてくることがある
ものを売るといったことを
一生知らないで終わる者がいるが
ものを売るためには
相手にしらさなければならないという
ごく簡単だが
とても重要なことがある
寒さがどんなものであるか分かっているが
納豆を抱え声を出して歩く寒さを
わたしはしらない
ナットー ナット ナット ナットー
少年が家の角を曲がってくるとき
とつぜんのように
その声が聞こえてくるのだ
すると おふくろが少年の名を呼び
納豆を求めるのだ
少年は経験から
どこをどう歩くと
納豆が売れるかということをしっていたのだ
少年は納豆を売るために
冬の夜明けの寒さを
味方に
それを頼りに歩いていたのだ
冬の夜明けにふるえていた声よ
(少年が十四か十五歳で
亡くなったという噂のような話が流れたのは
まもなくのことであったが
誰も確認はしなかった)
カナリアは何処か
危険を察知したのか
深い炭層の崩れて折れ曲がった隙間から
死者たちに別れを告げて
抜け出したカナリアの群れよ。
谷底から駆け上がりズリ山を掠めながら
どこへ羽ばたいて行ったのか。
都心部のアーケードを
潜って駐車場へ行かなかったか。
数十台のなかの一台。
そのちいさな後部座席の密室で
忘れられて熱中症にかかった幼児よ。
カナリアの鳴き声は 届かなかったか。
カナリアは幼児の泣き声を聞かなかったか。
あの子は泣くこともできなかったのだ。
あの太陽が灼けつくように かがやき過ぎた日。
アーケードに続くトンネルのような 地下回廊や
そこから枝分かれして 上に延びる階段。
デパートの エスカレーターやエレベーターの辺り。
売り場や レストラン 喫茶店の辺り。
涼しい顔が溢れていたが……。
涼しい顔が溢れていたが……。
競馬の有る日は アーケードには
ガードマンで溢れに溢れ、
強い馬を夢見て
靴をスリッパのように引っかけた、
男たちは タバコを吸いながら
幼い死者のことなどは 思ってもいない。
おれは おれ。他者は他者。
それはそうなのだが それはそうだとしても、
たとえば毎夜 あの家で
幼児三人が留守番だなんて、
星空の一角が崩れ落ち
火のトンネルとなって噴きだすなんて、
カナリアが のどを焼いて
いくら身を震わせても
鳴けなくなっていることなんて、
知りはしないのだ。